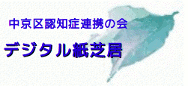マンガリーフレット「おばあちゃんが認知症になった」および そのデジタル紙芝居版で伝えたいこと -取扱説明書として-
このマンガリーフレットとデジタル紙芝居は、認知症について、小中高の教育現場での教材としての利用を想定して製作しました。その背景として、平成24年6月18日に厚労省から発表された「わが国の認知症施策の今後の方向性について」および、それに引き続いた「認知症総合対策5ヵ年計画(オレンジプラン)」に象徴される、認知症にたいする認識のおおきな転換があります。
認知症というのは、認知機能の障害であり、障害を抱えて暮らすためには出来るだけ早くから適切な援助が必要です。その援助が適切であるためには、家族・地域・専門職・行政といったすべてのレヴェルで、その障害について正しく理解することが必要なのは当然です。にもかかわらず、それが充分には行われず、往々にして、障害を持つ人の思いに充分な配慮を欠いた面があったのではないかという大きな反省に立って、一連の文書は出されたものとわたしたちは考えています。それはまた、個人が抱える障害への援助という個人支援に終始する視点から一歩も二歩も踏み出して、家族支援、地域支援へという広がりを見せているところが従来と大きく異なり、これが国家戦略ととらえられうる所以でもあると考えます。言葉を変えれば、認知症という障害を持つ人を抱える家族もまた、「家族」としての障害を持つことになるということでもあります。「地域」もしかりであり、それぞれの相における「障害」の理解と正しい対応を模索することが、「正常者による障害者の支援」という古いパラダイムを越える視点(ノーマライゼーション)を構築することにつながると考えています。オレンジプランの別称である「認知症総合対策」の「総合」には、国家的全体的なものより、comprehensive(理解のある) でcoordinative(協働的)なニュアンスを読み取ることが出来ます。
リーフレットではその序文で、認知症を「適切な援助を必要とする障害」と定義づけて、ノーマライゼーションの考え方を示し、「認知症を社会の重荷ととらえがちな大人」に対比させられた子供の真摯な表情に、この取り組みの継続可能性と今後への希望を象徴させています。子供が持つ「なぜ、どうして、どうしたらよいのか」という問いは、このリーフレットの中で、答えが十全に語られているわけではありません。むしろ通常の病気に比較して、診断治療の枠組みだけでは答えられないことを暗に示しており、それはどこかにある「神の書いた正解」を求めてただ待つ、つまり病名というラベルを得ただけで済ませてしまうのではなく、自らの行動に結びつく理解の必要性を強調してもいるのです。そこに、ケア、特に個別ケアとそのなかでのコミュニケーションの重要性が語られているのは、それが、成長期の子供たちの心の問題にも共通する構造を持っているからだとの認識を示しています。
それに続くマンガの本体では、戸惑うご本人の様子を子供の目を通して追う形で、現在のどこにでもある医療とケアの現場が親しみやすい画風で描かれています。入り口として一番一般的な医療と、そこからつなげられる介護と、そして障害の理解と受け入れに向かう家族の変化にいたる流れの中で、この子は、看護師になろうと心に決めています。それは、この子が、家族を思う「利他的」な、「ケアの原型」を持っていることを示しています。エピローグで、その家族共同体の中で生まれたケアの原型の20年後が語られます。
Q&Aでは、問いはいたって真っ当なものですが、答えは常にずれています。それははぐらかすためではなく、自ら考えてもらうためです。病気のことを問うているのに、宇治市の連絡表を見せられた子供たちはどのように考えるでしょう。認知症が「ガッテン」するように何かに還元できるものではないということはなんとなく思うでしょうし、それとともに、社会の取り組みが、医療だけではない大きな広がりがあるのを感じてくれるでしょう。ケアのことを聞いて、京都式認知症ケアの十か条を教えられても、眼を白黒させるだけだと思いますが、「何で京都式なんだ」と疑問を感じてくれれば次の問いを見つけることができるかもしれません。三つ目の問いで原因を問わないで、原因がわからない理由を問うのは、もうすでに原因はわからないのではないかということを含意していますが、答えはそれを肯定する形で現状ではという留保をつけながら「何かのせいではないし、まして誰かのせいということはない」という疾病観の枠組みのひとつを示しています。四つ目の「老人を発見した21世紀」という答えには、認知症に対する希望、国や地域での取り組みを表現しており、さらには「子供を発見した20世紀」を引き合いに出すことで、あらためて子供たちにも社会や歴史に思いを伸ばしてもらいたいという意図もあります。そして、最後の問いでは、身近ないじめの問題などを連想させながら、より普遍的な「ルールの共有」という言葉で、言葉を超えた理解の必要性を示してQ&Aはおわります。その充分な答えになっていない答えには、大人にこそその問いを(現実の社会で)解いてもらいたいという作者の思いが隠されていますが、大切なのは「なぜと問うのと同じくらいどこへということを考えること(E.H.カー「歴史とは何か」より)」なのです。
最後の20年後のエピローグでは、「介護」という言葉では見えにくいケアの双方向性を、実際のメディアに現れた子供の言葉を拾いながら示しています。時計を20年後に設定したのは、デンマークでも、1990年ころから施設収容型から在宅への転換が始まって今の形ができたように、わが国でも20年後にはそうした体制ができていてほしいという希望がこめられています(物語ではそうした何かができていることを暗示しています)。最後にふれたように、人生を祭りやカーニバルにたとえるのは洋の東西を問いませんが、主人公が例えにあげた、溺れた友人を助けて命を落とすカンパネルラ、このなまえは旅人の魔よけの鈴をさし「ともに行く者」という意味もあるようですが、彼の聞いた祭りのざわめきとは、賢治作品のイメージに繰り返し現れる時間という次元を含む宇宙、時空を超えた四次元の世界観を暗示しています。身近な現実の祭りを例に挙げなかったのは、「祭り=人生」という通り一遍の理解(クリシェ)ではなく、銀河鉄道の夜という賢治の世界観を通じて、イラストにあるように、目の前の老人に、その人の人生の複雑に重層された過去現在未来のつながりを見てもらえたらという強いねがいによるものです。
<<デジタル紙芝居のページに戻る
|